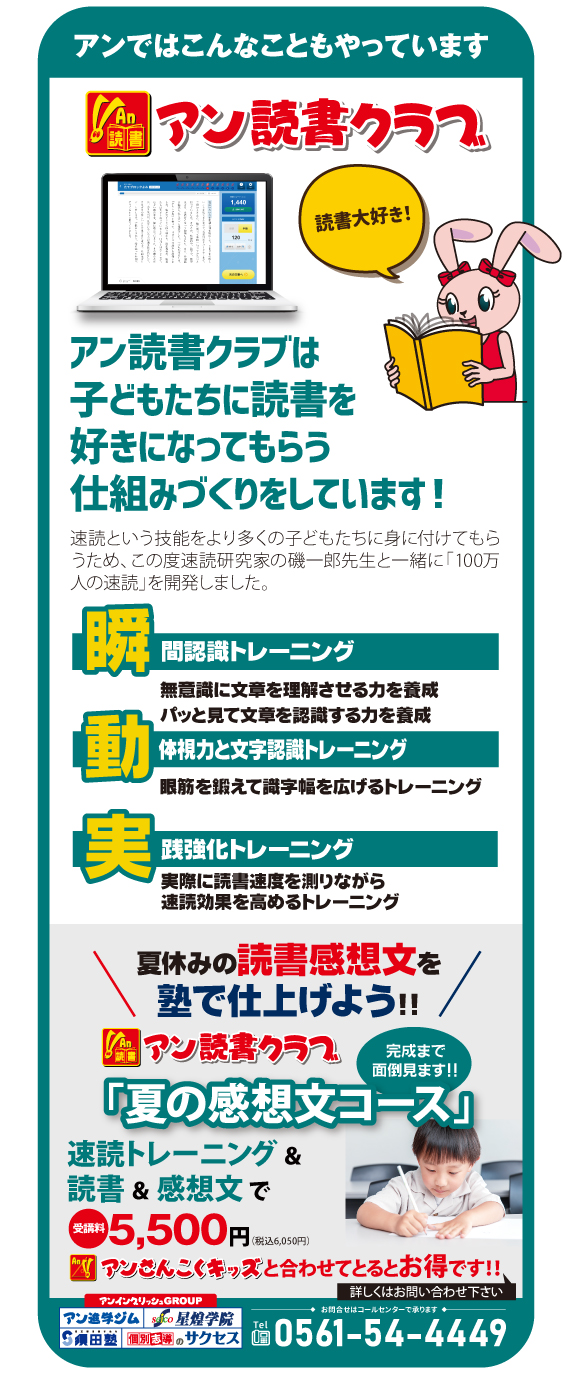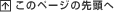酒井:先生方今日はoh!とくだね読者の方々にアドバイスいただくためにお越しいただきありがとうございました。今日はよろしくお願いいたします。
近藤・大田:よろしくお願いいたします。
酒井:私は昨今の入試問題が長くなっているのは、ネット社会の到来により10年前や20年前とは格段に違う量の情報が様々な組織、団体及び個人から発される時代になり、社会人として処理しなければいけない情報量が格段に増えたことに由来するのではないかと考えていますがいかがでしょうか?
入試問題が長文化している
近藤:はい。私も同感です。一般の日本人の読書スピードは1分間に400文字から600文字と言われています。つまり話すスピードと同じと言われているんですね。そのスピードで制限時間内に正解を導き出すことは、昨今の共通テストの文章を読んでいると難しいのではないかと思います。
大田:本当にそうです。来春より愛知県でも始まる公立中高一貫入試ですが、愛知県においてどのような入試問題が出題されるかはまだまだ未知数ですが、他府県の公立中高一貫校の入試問題は共通テストに負けず劣らずといった長文揃いです。
 酒井:そうですよね。共通テストは高校生の受けるテストですが、公立中高一貫校の入試は小学生が受ける入試ですよね~。その入試でも長文化の流れはすごいですよね~。
酒井:そうですよね。共通テストは高校生の受けるテストですが、公立中高一貫校の入試は小学生が受ける入試ですよね~。その入試でも長文化の流れはすごいですよね~。
近藤:公立中高一貫校の入試も長いですが、私立中学の入試問題は長いだけでなく、かなり難解な文章も出題されますから、速読力の養成はもちろん大切ですが、熟読力というか堅固な読解力が必要ですね。
読解力と熟読力について
大田:速読というと時々「飛ばし読み的な読書法なのか?」と誤解を受けることがあるんですが、速読は決して軽く読み流すのではなく、読むトレーニングを受けて速く読めるようになっただけで、決して飛ばし読みをしているわけではありません。
近藤:読む時、人の目は行の一部を塊で捉え、次々と隣の文字の塊へ視点をずらして読み取っています。また「精読」と言っても必ずしも1文字ずつ見て読んでいるわけではありません。文字列をまとめて見てその字の塊が自分の記憶にあるもの・ことを紐づけて認識するとともに、そのイメージの連なりをストーリーとして捉えたものが、あらすじとして記憶されているのです。
読み取るその文字列の塊が20文字になり1/2行~1行になっていくと、それにつれて視野が拡大します。やがて2行まとめて→3行→半ページ→1ページと読む視野も広がり、結果としてページのめくり読みにつながっていく。その感覚がわかると「これを続ければ速く読めそうだ!」という自信に繋がり、“速く読めれば面倒くさくなく何度でも読める”ことが、体感できます。
速読ができると読み直し=重ね読みの時間が取れますから、むしろ精読も出来て内容の深掘りができることになります。
酒井:速読についてとかく誤解されがちなそのことを生徒たち、そして保護者の方々にしっかり理解していただけるように説明していきたいですね。

 大田:実際に普通の大人の読書スピードは1分間に400~600文字(話すスピードと同等)と言われていますが、東大や京大合格者の平均読書スピードは1分間に約2000文字程度といわれています。一方で読書が苦手な小学生の読書スピードを測ってみると250~300文字程度であることが多いようです。
大田:実際に普通の大人の読書スピードは1分間に400~600文字(話すスピードと同等)と言われていますが、東大や京大合格者の平均読書スピードは1分間に約2000文字程度といわれています。一方で読書が苦手な小学生の読書スピードを測ってみると250~300文字程度であることが多いようです。
酒井:つまり文章をあまり読まないと思われる小学生は約250文字に対して、文章をよく読んでいると思われる東大生・京大生は1分間に約2000文字ですから、多読習慣をつけることで、読書スピードが上がるということが想定されるわけですよね?
読書ぎらいを読書好きに
近藤:はい。その通りです。多読をすれば慣れも手伝って、読書スピードは速くなるものと思われます。そうでないと上の事は説明が付かないですから。しかし、何らかの理由で読書嫌いになってしまったお子さんに普通に多読をさせて読書スピードをアップさせることは無理なわけです。(そもそも読むことが嫌なのですから)そんなお子様には先に速読を身につけてもらうと実は読書嫌いが直るんです。そういう子ども達を多数育てて来ました。
酒井:私の指導経験上からも、子どもたちに速読トレーニングを行って、子どもたちの読書スピードが1分間に900文字を超えると、自然に多くの子どもたちが本を読むようになったと保護者の方々から言われたことがあります。
大田:今の子どもたちは面倒くさいことが大嫌いです。だから1分間に250~300文字のスピードだと話すスピードの半分ですから、そのスピードで情報取得するのはとっても面倒くさいですよね。それが900文字になると話すスピードの1.5倍ですから、むしろ人から話を聞くよりも本を読んだ方が情報取得が速くなるわけです。たぶんそのスピードを超えると、本読みが面倒くさいことから、面倒くさくないことに変わったんだろうと予測できますね。
酒井:つまり読書スピードが速くなった結果、今まで面倒くさかった読書が、面倒くさい事でなくなったと考えられるわけですね。
近藤:ある意味、読書をするのではなく「速く読めることが目的になる」わけです。すると、自分自身や友達との競争原理が働きますよね!
読書スピードを上げるためには
速く読むためのトレーニングとしては、①視野を広げる、②行を2~4つの塊で捉える、③見る行数を増やしていく、という具合にトレーニングしていきます。
大事なことは、絶対に覚えるように読まないことです。“えっ、覚えないの???”と思われるかもしれませんが、ここが脳科学に基づいた100万人の速読らしい大きなポイントです。
そして④限界まで読書スピードを上げる「インターバルトレーニングを繰り返す」これでどんどん読書スピードを上げていくのですが、ここにも大きなポイントが…。

実は、速聴とめちゃくちゃ相性の良い「可塑性を高める」練習方法になっていて、eduplusの学習にもとても相性がいいのです。
大田:可塑性とは使えば使うほど柔らかくなるといった脳の特性の事で、変幻自在の働きの事です。速聴の補足含めて少し脳科学的な説明をしますと、原則的に、理解しながら文章の内容を聞く、読むというのはイメージ的に左脳を使う形となります。ここの箇所では正直可塑性の働きは見られません。しかしながら、スピードに慣れる作業、右脳を使うという領域でようやく可塑性の働きが見られます。
実は、頭の回転を速くすることは、年齢に関係なく、トレーニングによって誰でも確実に獲得できる能力です。頭の回転をよくすることでキャパを広げたり、処理能力を獲得することで、結果的に速読にみられる理解をしながら早く読むことが可能になるのです。
速読で理解力も深まる
速聴とは、パンと手をたたくと音が聞こえるように、速さや大きさの測定ができるという利点と聞くより聞こえるといった、ある意味受け身の形で捉えることが容易な点が特徴です。速聴のスピードに慣れて速読につながると鬼に金棒! eduplusの4倍速のスピードで学習できることも含め、速聴、速読を身につけると本日の議題である速く読む、理解力も深まることが可能になるのです。
酒井:速読も速聴も可塑性が一つのキーワードの様ですね。左脳を使って文章を読む手法から、右脳も使って文章を読むという、習慣作り(読み方のくせ)を行うトレーニングを積むことにより、読書スピードが速くなるそんな感じですね。
近藤:全くその通りです。私は日本中の子どもたちのみならず、老若男女問わず速読を身に付け、よりたくさんの文章(情報)の中から、自分にとって有益な情報を探り出し、豊かな人生を送ってもらいたいと考えて速読の普及活動に勤めています。
酒井:近藤先生、大田先生、本日は「速読」「速聴」に関する貴重なお話をありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。